| Appendix 0 理想気体 | ||
| f-denshi.com [目次へ] 更新日: 執筆中 | ||
| サイト検索 | ||
初学者は気にしなくてもよいのですが,少し注意事項を話しておきます。
高校でも習う理想気体の状態方程式は,熱力学の基本法則ではありません。
熱力学の基本法則は,熱力学第0法則から第3法則までの4つだけです。
それにも拘わらず,〜の法則というものが熱力学にたくさん現れる理由は,学問体系の理論的な整備が行われる前に現象論的な観測が行われ,その結果を発見者の名前を付けて,「〜の法則」と呼んでいた名残りと考えられます。化学熱力学分野では,ボイル・シャルルの法則,ドルトンの法則,ルシャトリエ・ブラウンの法則,質量作用の法則などがそれにあたります。
古典力学も眺めてみましょう。ニュートンの3つ法則 (慣性の法則,ニュートンの運動方程式,作用反作用の法則) は基本法則です。しかし,ばね・弾性体の復元力に関する「フィックの法則」は古典力学の基本法則ではありません。これは基本法則を適応させた数学モデルにすぎないのです。
ある現実の系に対して,フィックの法則が成り立つという言い方がされたときは,正しくは,その系はフィックの法則で規定される数学モデルを利用して解析可能だという意味で捉えるべきです。
熱力学に話を戻すと,理想気体の状態方程式は,古典力学のフィックの法則と同様な立ち位置にあって,熱力学の基本法則を適用させて,イジリ回す気体の数学モデルにすぎなく,基本法則ではないのです。
しかし,そこから導かれる結果はすべて限定的なものかと言えば,そうとは限らないのです。非常に適用範囲の広い有用な概念(例えば,エントロピー)が得られることもあるのです。
[1] ボイル-シャルルの法則から説明しましょう。
(1) 希薄気体の体積V は圧力P に半比例する,PV=一定。(ボイルの法則)」
(2) 希薄気体の体積V は温度T に比例する,V/T=一定。(シャルルの法則)」
以上,2つを合わせた法則をボイル・シャルルの法則といい,関係式で表すと,
V ∝ T P
もちろん,これら気体の状態変数V,P,Tの関係は限られた物質・実験条件のもとでしか成立しないのですが,この関係を厳密に満たす気体を理想気体といいます。これらに加えてさらに,気体が無秩序に運動する分子の集まりからなることを認める(現在,これは常識となっていますが,熱力学黎明期には仮説でしかありませんでした。)と,気体の体積V はそこに含まれている分子の数,つまり,モル数nにも比例するはずです。以上をまとめて表すと,
V ∝ nT P
そして,この比例定数をRで表すと,2章で示した理想気体の状態方程式にたどりつきます。
|
理想気体の状態方程式: PV =nRT |
[2] 次に理想気体の内部エネルギーについて考えてみます。内部エネルギーは分子論的には分子のもつ全運動(並進,回転,振動)エネルギーと分子間ポテンシャル(双極子間の相互作用など)との和に相当するものです。
理想気体が適用可能な希薄気体の「希薄である」 ことの分子論的な意味を書き出すと,
(1) 分子間相互作用
(2) 排除体積
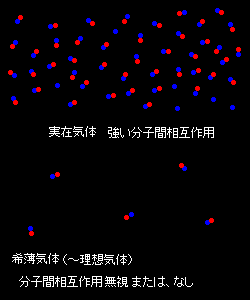 が無視できる ことにあります。つまり,希薄な気体を考えるときは,一つ一つの分子のすぐ近くに別の分子はほとんど場合存在せず,真空中をほとんどの時間,単独で飛び回っていることになります。そして理想気体とは,この高密度で顕著となる効果(1),(2)を気体の密度に関係なくいつでも無視することが可能な気体ということができます。(厳密に言えば,理想気体の状態方程式に従うことと,この2つの効果が無視できることは同値ではないが。)
が無視できる ことにあります。つまり,希薄な気体を考えるときは,一つ一つの分子のすぐ近くに別の分子はほとんど場合存在せず,真空中をほとんどの時間,単独で飛び回っていることになります。そして理想気体とは,この高密度で顕著となる効果(1),(2)を気体の密度に関係なくいつでも無視することが可能な気体ということができます。(厳密に言えば,理想気体の状態方程式に従うことと,この2つの効果が無視できることは同値ではないが。)
さて,分子間相互作用,排除体積ともに分子の持つ静電ポテンシャルにおおむね基づいていますが,分極(極性)を持った実在分子だと分子間相互作用はそれほど密度の高くない気体でも無視できません。
一定量,例えば1モルの気体を圧縮して体積を減少させると,平均の分子間距離が近づくことになり,分子間の相互作用(=静電的エネルギー)は距離が近づくと大きくなるので,温度が同じであっても内部エネルギーは変化します。つまり,運動エネルギーの一部は静電ポテンシャルエネルギーに変化することになります。理想気体では分子間の相互作用がないので,どんなに小さな体積に分子を閉じ込めておこうとも,系の内部エネルギーは一つ一つの分子が持つエネルギーの単純和(各分子の力学的エネルギー)でしかなく,全運動エネルギーも変化しません。つまり,1分子あたりの平均運動エネルギーに比例する温度ります。このようすを,
「温度が同じならば,内部エネルギーは気体の体積に依存しない。」
ということができます。理想気体はこの性質を満たすこととします。
分子運動論的な考察 ⇒[#]
[2.5] これは,dU=TdS−PdV [#] とマックスウェルの公式(15)[#],および,圧力係数:γp[#] を用いて,
∂U = T ∂S −P ∂V T ∂V T = Tγp−P
=T ∂P −P ∂T V
と表しておき,理想気体について,
γp= P T
である[#]ことを用いると,
∂U = 0 ∂V T
として計算で示すこともできます。
(読んではいけない! これは内部エネルギーが温度Tのみの関数で,体積Vによらないことの証明のように見えるが,状態量エントロピーSの存在を前提としており,結局,エントロピーが状態量であることと理想気体の内部エネルギーが温度のみの関数であることが同値であることを示している(証明の一部分)に過ぎない?以上,読んではいけない。)
Cp = Cv + ∂U +P ∂V ∂V T ∂T P
に代入し,1モルの理想気体に対する状態方程式 V = RT/P を適用すると,
Cp = Cv + P ∂V = Cv+R ∂T P
つまり,
理想気体のモル比熱について, Cp = Cv+R (1mol に対して) [マイヤーの関係式(Mayer's relation)]が成り立つ。 |
理想気体の定圧モル比熱の方が等積モル比熱よりRだけ大きくなります。これは定圧条件下で系に加えられた熱は温度上昇のためだけにではなく,気体が同時に膨張することによる外部へ仕事としても使われるため,等積変化の場合に比べて余分の熱を系に投入しなければ,同じ温度上昇につながらないからです。そして,定圧条件下で気体の温度を1℃上げる際に気体の膨張によって系が外部になす仕事がRなのです。
[4] 気体の分子運動論 [#]から単原子分子について,
PV= 2 U =RT [ Bernourlli の関係 ] ←熱力学の中では導けません。 3
この関係を借りてくると,比熱は具体的に表すことができます。すなわち,定積比熱 [#] は,
Cv= ∂U = 3 R [単原子分子] ∂T V 2
したがって,
Cp= 5 R [単原子分子] 2
つづく,